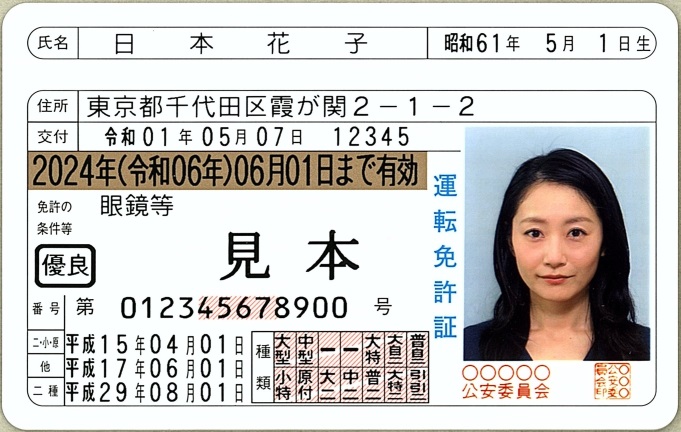
運転免許には、いくつかの種類がある。そのうち、「普通自動車」「中型自動車」「大型自動車」といった、車両の種類によるものは「区分」と呼ばれている。同様の分け方は道路運送車両法・高速道路通行区分・税区分などでも見られるが、運転免許は道路交通法に基づいたものであり、それぞれ微妙に違いがあるのだ。
もうひとつの分け方が「種類」で、「仮運転免許(仮免)」「第一種」「第二種」となっている。「仮免」は読んで字のごとく「仮」に発行される免許で、運転免許を取得しようとする人が一定の条件の下、公道上で練習する際に取得するものだ。多くの人が持つ「第一種」は、車両を自家用として運転する際に取得する免許である。
「第二種」はお金をもらって人を運ぶ場合、すなわち客を乗せて営業をする車両を運転する際に必要な免許。これは、旅客営業のバスやタクシーだけを指しているのではなく、運転代行で客を乗せる場合や、有償の送迎を行う場合も含まれている。逆に、旅館の無償送迎や幼稚園バス(共に自社の管理する車両を自社従業員が運行する場合)などでは必要がない。また、今話題のライドシェアも「第一種」を所持していればよい。

ここで注意が必要なのは、原動機付自転車にみられる「二種」である。これは、正式に「第二種原動機付自転車」といわれるもので、道路運送車両法に基づいて原動機付自転車を排気量によって分類したものだ。運転免許の「第二種」は、先に触れたように道路交通法に基づくものなので、まったくの別物なのである。
運転免許の「第二種」は、運転できる車両によって5つの種類がある。「普通自動車二種免許」は、主にタクシーやハイヤーの運転をする際に必要になる。運転代行で客を乗せる場合も、たいていはこの免許だ。「中型自動車第二種免許」は、マイクロバスなどで旅客営業を行う運転手が所持している。大型・中型の路線・観光バスなどになると、「大型自動車第二種免許」を持たなければならない。

「大型特殊自動車第二種免許」「牽引第二種免許」もあるが、これらは、人を乗せて営業をする車両がほとんど存在しない。そのために免許保有者はたいへん少なく、運転免許統計2025年版(警察庁発行)によると、大型特殊で1744名、牽引は506名である。ただ、近年増加傾向にある連接バスの運転に、「牽引第二種免許」の保有を条件にするバス会社が増えているという。本来連接バスは牽引免許を必要としないが、操作や動きが牽引車両に近いことから、そういった動きになってきているのだそうだ。
ただ、「二種免許」の取得は意外に難しいといわれている。受験資格年齢は、21歳以上。受験予定の免許以外の第二種免許を取得しているか、第一種の大型免許・中型免許・準中型免許・普通免許・大型特殊免許のいずれか(牽引二種の受験には牽引一種の取得が必須、そのほかにも例外規定がある)を取得して、3年以上保持(免許停止期間を含まない)している必要があるのだ。

試験は適性検査・学科試験・実技試験の3種類で、学科試験は正答率9割以上なければ合格しない。合格率は「第一種」が9割を超えているのに対して、「第二種」は6割程度に留まっている。このことからもわかるように、この免許を持つドライバーは、まさにプロ中のプロ。所持していれば、自慢できる資格といえるのではないだろうか。
