
近年、わが国では少子高齢化が進んできた。特に、地方都市においてその傾向が顕著であり、クルマが必要な地域でも高齢者の免許返納を見据えて、公共交通機関の運行体系を見直す必要に迫られている。一般に、地方都市の公共交通機関といえば民間事業者が運営する路線バスだが、その収益性は必ずしも高いとはいえず、相応の客数が見込めなければ経営が成り立たない。
そこで、自治体の支援を受けたコミュニティバスを導入するところが増加し、運行は委託を受けた民間運輸事業者が行なうといった例が増えているのだ。これに使用されるのは、マイクロバス・ミニバン・タクシーであることが多い。中・大型バスを使用する路線バスに比べればイニシャルコストは下げられるし、ランニングコストも少しは抑えることができるだろう。しかし、1台に1名の運転手が必要なことは変わらない。そもそも、高齢化が進んでいるのはバス・タクシーの運転手も同様で、担い手の確保に四苦八苦している状況なのだ。
結果的に、行き着くのは自動運転車両の導入ということになる。それは、香川県にある小豆島の土庄町(とのしょうちょう)でも同様で、同町では自動運転バス(レベル2:アクセルやハンドルを自動制御して運転手をサポートする、本実証では遠隔監視装置を併用)の運行実証実験を、2024年9月12日~17日の6日間にわたって実施した。
いうまでもないが、レベル2の自動運転は運転手が乗車しなければならない。車両も特殊なものなのでイニシャルコストもランニングコストも、路線バスを上回る可能性が高いのだ。しかし、これはあくまでも中間地点であって、見据えるゴールはレベル4(操縦はシステムが主体で行ない、特定条件下で完全自動運転を実施する)である。

この実証実験は「20年先の小豆島をつくるプロジェクト」の一環で、第1弾の「シェアサイクル事業」に次ぐ第2弾にあたる。同プロジェクトは旅行代理店が中心となり、地域行政や民間事業者が自主事業の開発などを通じて、観光地の価値向上と持続可能な発展を目指したものだ。2024年8月から、エリア開発事業の一環として小豆島でスタートしている。
今回の実証実験で使用された車両はMinibus(Tier4.製、15人乗り電気バス)で、土庄港高速艇ターミナル(平和の群像前)からエンジェルロード公園(小豆島国際ホテル)までの約2㎞を走行。1日7往復走って、運賃は無料であった。9月中旬の連休をはさんだ期間であったため、地元の人のみならず観光客の利用も多かったという。乗客にはアンケートを実施し、自動運転バスの感想や課題・必要性などに関する意見を収集した。
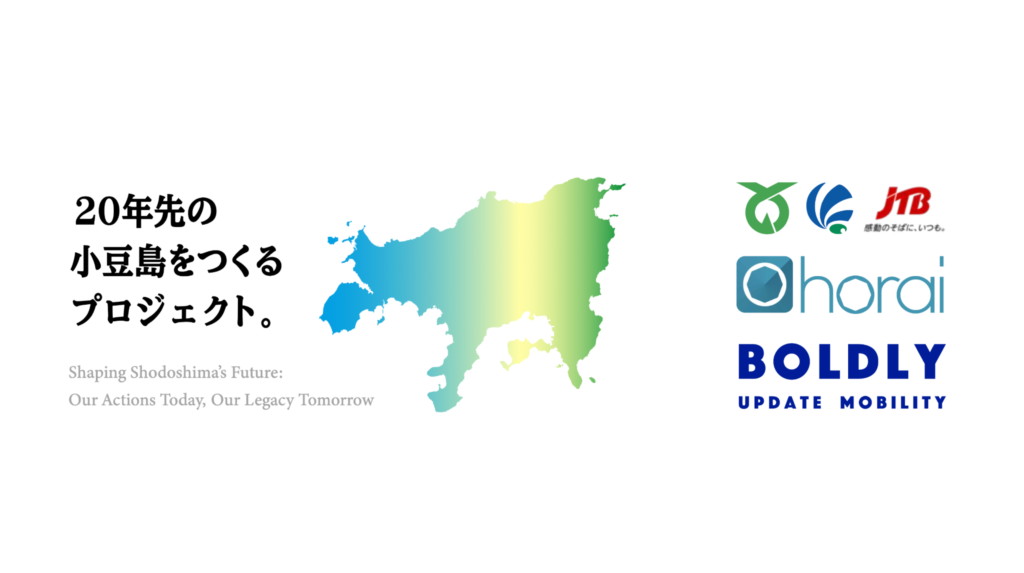
小豆島は小説「二十四の瞳」の舞台などといった観光資源を多く持つことに加えて、インバウンドの追い風により観光客は増加傾向にある。ところが、来島者の7割が日帰りであるために期待する経済効果が得られていない。その原因は宿泊施設や飲食店などが少ないことに加えて、二次交通(島内到着後の移動手段)の脆弱性が指摘されている。
今回の実証実験を始めとする同プロジェクトの推進で、小豆島と土庄町の活性化に期待が寄せられているのである。
